Thank you for your access.or This page automaticaly jumps to PDF version in 10 sec. to.pdf-page Go!
|
全ての画像には著作権があります。画像の無断使用をお断りいたします。
雨乞山(あまごいさん)愛知県渥美半島田原市石神
雨乞山
Amagoi-san ; aichi
泰山の古代遺跡探訪記
Presented by…
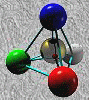 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.
愛知県渥美半島田原市石神の雨乞山(あまごいさん)を訪ねた。
渥美という地名は長野県安曇野の安曇と同じで、海人(かいじん)族である安曇氏に由来しているといわれる。
海積(あまづみ)が安曇(あづみ)の元になっており、海部(あまべ;丹後一宮籠神社宮司が海部姓)族の首長を意味するそうだ。
後世になって安曇は「安住」「安積」「阿曇」「阿積」「厚見」「厚海」「渥美」「英積」などに多様化したといわれる。
物部、安積、穂積、忌部は海人属の系統で、美濃、尾張、山科、奈良に広がる。のち、生駒、葛城にニギハヤヒ王権が誕生し、
やがて政権移譲が起こり神武朝へとつながる…と、日本正史を研究している私の友人から教えてもらった。
つまり渥美は物部系にとって因縁浅からぬ場所といえる。美濃、尾張、三河は巨石の宝庫でもある。
なぜ、それを記すかと言うと、ニギハヤヒは小生の『呼ばわりの神』であり、小生の巨石探訪には色濃くその影響があるのと
同時に、実際の巨石探訪においてニギハヤヒ、物部系統の深い関わりをそこに感じているからである。
この秋、半島の先端近くにある雨乞山を探訪した。
渥美半島は伊良湖岬や日出(ひい)の石門、恋路ヶ浜などで有名であるが、半島内部に行くことは殆どまれと言って過言ではないだろう。
渥美半島は20歳の時と40歳のときにも訪れていることを考えると、今回の探訪にもやはりその前哨戦があった思いがし、感慨深いものがある。
昔は流刑地にもなっていたこの辺境の地に(実際にアクセスはしにくい)三度訪れるわけだから、関わりの深い土地であることは確かである。
雨乞山には、その名の通り雨乞いを行った祭祀遺跡がある。雨乞神社として祀られたそれは山頂ほど近くの巨大磐座の小さな洞窟内にある。
渥美半島の最西端、伊良湖岬から国道259沿いに東進する。15kmほど走ると何やら気になる「石神」
という村落にでる。この石神が雨乞山登山の起点となる。
初めての探訪で雨乞山にアプローチするのはかなり厄介である。登山口が非常に分かりにくいのだ。
山自身の存在はすぐに分かるのだが、なかなか入口にたどりつけない。私も現場で20分程も入口を
探し、二人の農作業の人に助言をもらい、ようやく入口を見つけることができた。
雨乞山の岩質は渥美半島を抜けて愛知県新城の鳳来寺山へと続く。探訪の足は当然そこにも向かうことになる。
渥美半島は中央構造線上の西南日本外帯の北端にある。中央構造線は半島の伊良湖岬と立馬岬
の中間を通り、渥美半島の北岸沿いを走っている。
この半島は200m級の山地部、台地部および低地部によって構成されている。
半島全体は堆積層の隆起によって形成され、雨乞山を含む山地部は約2億5000年前に形成された
砂岩、泥岩、礫岩、チャート*、石灰岩による累層;堆積岩コンプレックスとなっており、秩父帯付加コン
プレックスと呼ばれる。したがって渥美半島の山には花崗岩はない。
中央を横断する山岳地帯の北側は穏やかな田園風景が広がる低地であり、山頂からは三河湾が望
める。
*チャートとは陸から離れた深海底で堆積した放散虫というプランクトンの殻が固まった岩石
探訪;2007年9月 記;2007年10月 泰山

地図001
渥美半島は愛知県の南端にある半島で、知多半島と共に三河湾を取り囲んでいる。
渥美半島の最西端に伊良湖岬があり灯台とフェリー乗り場で有名。伊良湖岬そばの浜は恋路ヶ浜として知られ、
そのすぐ傍には海中に突き出た大きな穴のあいた巨大岩塊「日出(ヒイ)の石門」がある。
石門の北の大地には伊良湖神社がある。
恋路ヶ浜は、「名も知らぬ、遠き島より流れ寄る椰子の実ひとつ・・・」という椰子の実の詩の舞台となった場所としても有名。
石垣島をその「遠き島」に設定し、毎年石垣島からしるし付きの椰子の実を流したところ、14年目の2001年8月3日に渥美半島の浜辺に椰子の実が漂着したそうだ。
椰子の実の話は明治時代に柳田國男が伊良湖岬を訪れた際に地元から聞き、それを友人の島崎藤村に伝えたところから有名な詩が生まれた。
また、江戸時代には松尾芭蕉が愛弟子の杜国を保美の里に訪ねている。
「鷹一つ見つけてうれし伊良湖崎」
雨乞山は国道259沿いの石神地区にあり、三河湾に面している。

写真001
日出の石門(ひいのせきもん)の案内板。石門はチャートでできている。太平洋プレートの移動に乗って形成された。
海底で形成された堆積岩の層がよく分かる。断層の崩壊部分が長い年月をかけて波に浸食され、有名な海食洞となった。
日の出を拝める場所としても有名である。岩質は目的の雨乞山のものと全く同じである。

写真002
遊歩道沿いから撮影した日出の石門の全景。

写真003
高さ約20m、長さ約40mの巨大岩塊。中央が海食洞穴。

写真004
海食洞穴部の拡大写真。

写真005
日出の石門の右遠方に伊勢湾に浮かぶ神島を望む。

写真006
栲幡千々姫命 を祀る伊良湖神社。戦前は伊良湖岬にある宮山の中腹にあった。
天照大神の子の正哉吾勝勝速日天忍穂耳尊が、高皇産霊尊の娘の栲幡千々姫命 を娶り、天津彦彦火瓊瓊杵尊 を生んだとされる。
三河国内神明名帳には「正三位伊良久大明神」と記されている。格式の高い神社である。

写真007
伊良湖神社の社殿。

写真008
伊良湖神社境内にある、本殿と真向かいの石と石の囲いを社とした小社。

写真009
一番高いピークが雨乞山の頂上。その左の2番目のピークも雨乞山の一部。
雨乞山は中腹に一つのピークを持つ山で、頂上付近は美しいピラミッド状をしている。
国道259を石神で右折すれば雨乞山の姿を確認できる。…が、そこからのアプローチが極めてややこしい。
県道を一本奥に入った地方道を進み、貯水施設が見えるあたりでさらに山中に入る。
その貯水施設脇にクルマをとめて登山をすることになる。

写真010
これが貯水施設。比較的大きいのですぐに確認できるだろう。ここにクルマを止める。

写真011
貯水施設の脇から雨乞山の登山道が始まる。標識も出ている。

写真012
登り始めからいきなりの急坂が続く。200mほど張られたロープを伝って登ってゆく。
既に登山道には秩父付加帯コンプレックスと呼ばれる堆積岩が露出し始めている。

写真013
もう一つの小さな気色の悪い貯水槽にたどり着く。ここを過ぎれば山道らしくなってくる。
帰りは道に迷いやすいので、この施設をしっかりと記憶しておいた方がよい。

写真014
堆積岩でできた階段状の山道。登山道自体はたいへん心地よいものがある。

写真015
第一のピークが見えてくる。

写真016
第一のピークあたりで見晴らしのきく場所に出る。登ってきた道を振り返るとそこにはのどかな田園風景と三河湾が広がっている。

写真017
雨乞山中腹の東方向の側壁に突き出している大きな岩塊。

写真018
頂上間近にある階段状の堆積岩。

写真019
ほぼ頂上に着いたところで振り返ったところ。頂上部は全体が岩塊となっている。写真17で横に見えた側壁の突き出しがこんどは
右下に見えている。

写真020
雨乞山の山頂。標高237m。海岸レベルから直接登るので実際に200m以上の登りとなる。貯水施設から40分程度の距離。
左手の美しいピラミッド型の山は「みはり山」

写真021
同じく頂上。秩父付加帯コンプレックス;堆積岩による磐座である。遠方は三河湾。

写真022
頂上磐座の全体像。アカタテハと思しききれいな蝶が優雅に舞い、歓迎の意を表してくれた。

写真023
アカタテハの舞を捉えたベストショット!最高の瞬間。
雨乞山周辺には鸚鵡(オウム)石、トンビ岩、恐竜の背など伝説のあるものや特別の名称がついた巨石が存在している。これらの巨石も岩質は堆積岩である。

写真024
これが『雨乞岩』と称することができる雨乞神社の御神体。
実際には写真の数倍も大きさを感じる超巨大な磐座である。
下部中央に洞窟があり、小さな祠が祭られている。
ここで雨乞いの儀式がとり行われた。
この磐座は山の岩質と同じで堆積岩。
この磐座こそがまさに「石神」であると感じた。地名の石神もそこから来ているのではないかと思うのだが…

写真025
磐座と祠は北を向いている。すなわち三河湾
に面している。
右は雨乞神社の祠と洞窟のクローズアップ。

写真026
御神体『雨乞岩』を横からみたところ。

写真027
御神体『雨乞岩』前の樹木。
磐座のパワーが垣間見える。

写真028
雨乞山となりにある、これも美しいピラミッド状の小山。
探訪所感
渥美半島の山々もなかなか風情のあるものである。この半島の山はほとんどすべてが砂岩、礫岩、泥岩、チャート、石灰岩からなる堆積岩で形成されている。
花崗岩に出会うことが多いピラミッド山と巨石探訪において堆積岩の山というのはまた別の趣がある。
ピラミッド山の概念構造(新人物往来社;別冊歴史読本#80にて執筆)から言えば、雨乞山は雨乞神社の磐座という明確な“陰の空間”を持ち、
頂上には岩塊としての磐座があり、周辺に複数のピラミッド型の美しい山々を有しているわけであり、またあらためてよく見ると雨乞山自体がピラミッド的な容姿をしていることから考えて、
石神の雨乞山もその地において構造体的機能を発揮する小型ピラミッドと考えることができるのではないだろうか。
現実、近年までかの雨乞神社の御神体の前で雨乞いの儀式が行われていたことを考えれば、この山が生活・文化に直接かかわる能動体であることに間違いない。
雨乞山の頂上から石神の村落を見下ろした時によく実感できるのだが、実に豊かな農村の風景がそこに広がっている。渥美半島は比較的温暖な気候に恵まれているが、
雨乞神社で雨の恵みを祈り、眼下に広がる田畑の豊穣を願ったであろうことは想像に難くない。
このように、山々と巨石のセットが生活文化構造体として生きていることが、実は日本ピラミッドの重要なところであるし、ピラミッドである証なのだと感じている。
2007年の探訪では、ことさらのように花崗岩ではない、石灰岩の山や今次のような累層岩の山を巡り、同時に“雨や水”に関わる事象を見てきた。
花崗岩のみならず、他の岩質の山と巨石についてもピラミッド構造体が形成しうるのではないかと確信するに至ったことは大きな収穫であったと思う。
岩質の差による、ピラミッド山の機能・役割の差などが今後探究できればさらに面白くなりそうである。
今回の探訪ではおしなべて、『蝶の舞による歓迎』を受けたことはまことに印象深い。
蝶は“霊的な媒体でもある”という言を、複数の人からこの夏耳にした。だから雨乞山山頂における蝶の歓迎も、晴天とも相俟って、
今回の探訪の意味を深慮するのにすこぶる味方してくれたのである。
泰山
泰山の古代遺跡探訪記topへ