Thank you for your access.or This page automaticaly jumps to PDF version in 10 sec. to.pdf-page Go!
|
全ての画像には著作権があります。画像の無断使用をお断りいたします。
天乃石立神社(あめのいわだてじんじゃ)奈良県奈良市柳生町789
天乃石立神社
Amenoiwadate-Jinjya ; Nara
泰山の古代遺跡探訪記
Presented by…
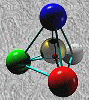 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.
京都府の笠置山を下山して、府道を南下すればすぐに”柳生の里”に出る。
柳生新陰流を興した柳生宗厳や独眼の十兵衛でおなじみの場所だ。
柳生の里は内陸部にある極めて穏やかなところである。
実はそこに気になる小山と巨石がある。小山の名前は戸岩山、巨石には天乃石立、一刀石などと名前がちゃんとある。
国道369号線を下り、右側に柳生中学が見えてきたら、いわゆるその辺りが”柳生の里”。
戸岩山と巨石へのアプローチはかなり分かりにくい。柳生中学から少し行ったところで国道369を左折する。
私の場合には殆どが直感である。「だいたいこの辺」というのが最も当たる。しかも重要なところで必ずと言っていいほど
”重要な人物”に出会うのである。今回もまさにそうであった。左折後少しばかり走ったところで稀に見る村人がこちらに歩いてくる。
やはりこういう場合には聞いておいた方が得策かと思い、訊ねた。
「あの〜、この辺に大きな石のある神社はありますか?」
村人はちょっと面倒くさそうに「この近くにあるけど…」と、いかにも質問されることに慣れている様子であった。
「この細い道を上がっていけば着くけど…、車では直接行けないよ」…指差したのがちょうどクルマを止めたところから分岐している
細い山道なのだった。
しばらく進むと、突然茶畑が出てくる。その先に鳥居が見える。ココだ!クルマを畑の手前で止めて少し歩いた。
やや無理をすれば小型車ならばその鳥居のところまではアプローチできそうである。
「天石立神社」と書かれた鳥居をくぐれば、パッと空気が一変し、いつも味わうあの巨石独特の雰囲気が漂ってきた。
観光的には真っ二つに割れた『一刀石』の方が有名かもしれない。名前の由来は柳生石舟斎が刀で切ったという伝説から来ている。
しかし、神社の御神体はこの一刀石ではなく、その手前にある三つの磐座である。その3つを総称して戸盤明神(といわみょうじん)あるいは神戸岩(かんべいわ)
あるいは天乃石立神社(あめのいわだてじんじゃ)という。
一刀石や戸盤明神がある一帯は岩戸谷と呼ばれる窪地のようなところである。小さなせせらぎさえある。そんなところに高さ20mほどの
戸岩山と呼ばれる小山がぽつんとあるのである。
今回は戸岩山自体には登る時間がなかったが、状況的には山梨県にある山梨岡神社;丸森山や岐阜県苗木の丸山のマウンドのように巨石が積まれたような
体裁をしている。しかも岩石は花崗岩である。
この戸岩山から大小の石がその山頂部分や中腹から転げ落ちているようである。ちなみに、神社内に祀られているきんちゃく岩は昭和28年に中腹から
転落した巨石であるとのことである。(それが現在は天照大神の岩になっているが…)
とするならば、一刀石自体も割れる前に戸岩山の上にあって、それが現在の所に転げた…と考えるのが順当だろう。
巨石の”割れ”については、別途深く考察する必要があるが、一刀石の割れは花崗岩特有の節理による自然分離にも見えるし、何らかの大きな力が全体的に加わり割れたようにも見える。
もちろん、いくら柳生石舟斎が剣の達人でも、この岩を刀で切ることはできないだろう。
御神体として祀られている三つの磐座の存在感はなかなか重厚である。まさに神が降臨するに相応しい形態でもあり佇まいでもある。
ということから考えて、一刀石はおそらく楕円状の花崗岩の巨石が戸岩山からいつの頃か大転落し、その衝撃で割れたと推論するのが
妥当なのではあるまいか。だから、一刀石はその”割れ”と”伝説”によって著名ではあるが、むしろ楕円球状の巨石が原体であり、それが
太古には(いつ頃かはわからないが)戸岩山の上部にあったことの方が重要なのだと思うのである。
戸盤明神の三つの磐座は形状的には極めて特異なものがあり、それゆえに祀られていると言える。そしてその傍には巨石を積み上げたようなマウンドがある…
という図式が最も注目すべき点であると考える。
戸盤明神;天乃石立神社の三つの御神体石とは、
後立磐(うしろたていわ)と呼ばれる櫛盤門戸命(くしいわまどのみこと)を祀る天岩吸(あめのいわすい)神社、
前立磐(まえたていわ)と呼ばれる豊盤門戸命(とよいわまどのみこと)を祀る天岩立(あめのいわたて神社)、
前伏磐(まえぶせいわ)と呼ばれる天磐戸別命(くしいわまどのみこと)を祀る天立(あまだて)神社、
である。
参考資料;『ピラミッド山の具象構造と概念構造』
探訪;2007年7〜9月 記;2008年1月 泰山

写真001
細い山道を上がりきると、開けた茶畑が…この先500m位の所にめざす神社と巨石がある。

写真002
「天石立神社」と書かれた鳥居。ここから岩戸谷に向かってやや下る。

写真003
式内天乃石立神社の由緒書き立札。

写真004
天乃石立神社の御神体となっている巨石群。手前が「後立盤」、後方の左右に角のような尖り部があるのが「前立盤」

写真005
「後立磐」と「前立磐」の間には微妙な隙間がある。花崗岩である。

写真006
「後立磐」と「前立磐」の次に出てくる「前伏磐」。
先端の形状からみて、「前伏磐」は「前立磐」から前に剥がれ落ちたものと言える。

写真007
「前伏磐」上端部と表面形状の拡大写真。この巨石の表面は3次元曲面である。

写真008
「前伏磐」と「前立磐」の関係。両者ともに左右上端部の突起が似ているのがわかる。

写真009
「後立磐」と「前立磐」との関係。100mm程度の隙間があいている。

写真010
「前立磐」が最も巨大。その上部と側面。

写真011
「後立磐」と「前立磐」の関係。逆のサイドから見たところ。

写真012
「後立磐」の表面拡大写真。苔むした良い佇まいの巨石である。

写真013
天石立神社の拝殿。最近リニューアルされたようだ。昔は拝殿傍に舞台もあったという。

写真014
天石立神社の説明板。

写真015
サイズ比較。私が手を付いているのが拝殿横の「きんちゃく岩」で現在は日向神社ということで天照大神を祀っている。「きんちゃく岩」自体はかなり巨大。これが
昭和28年に傍らの小高い戸岩山から転げ落ちてきたとのこと。

写真016
「きんちゃく岩」に横に入っている割れ目と甌穴状の凹部。割れ目は落下時の衝撃で入ったと推測できそうだ。

写真017
手力男乃命が開いた天の岩戸の扉がここに落ちた…旨の伝説がある。

写真018
これが「一刀石」…伝説では、柳生石舟斎(宗厳)が天狗を切ろうとして振り下ろした刀がこの巨石にあたって割れたことになっている。
たしかにそういう割れ方をしている。伝説化してゆくことによって、その対象が観光化され保持されるという点ではよいのではないだろうか。
ただし、巨石探究の視座からは、常になぜ、どうやって割れたのか。それがいつごろなのか。またどこからその巨石はやってきたのか。
巨石の原体はどういう形状であったのか、材質は何か…などについて考えておく必要があるだろう。
「一刀石」というのは優れた命名だと思うが、名称や現況のカタチのみから
その巨石を見るのは好ましくはないだろう。
ちなみに、「一刀石」の周辺は水はけの悪い湿地帯である。また、後方には小さめの洞窟状の陰の空間があり、そこに天狗らしき像が安置されている。

写真019
「一刀石」の”切り口”の拡大。花崗岩の節理かもしれない。落下の衝撃で節理面から割れたとも考えられる。
花崗岩によく見られる「鋭利な破断面とエッジ」

写真020
「一刀石」を見ていると、急に曇天が晴れ、雲間から太陽光が射してきた。灰色に渋く光る「一刀石」は非常に美しかった。
後方の小高い山が戸岩山。(岩戸山ということもある。)

写真021
戸岩山麓に転がっているいくつかの巨石の一つ。「一刀石」の近くにある。

写真022
巨石と光のハーモニー

写真023
戸岩山中腹にある巨石群。

写真024
同じく戸岩山中腹の巨石群。こちらの方は年代が古いと見え、苔がむしている。

写真025
天石立神社入り口付近は岩戸谷と呼ばれ、このような巨石群が夥しく存在している。おそらく戸岩山から崩落したものだろう。

写真026
戸岩山頂上部の巨石。今回は時間の関係で登れなかった。登れば必ず何か発見できると考えている。

写真027
戸岩山頂上部。小高いマウンドであることが分かると思う。

写真028
柳生の里の風景。柳生家家老屋敷より眺める里と古城山(だと思う)。

写真029
家老屋敷の門。現在は柳生関連の資料館となっている。

写真030
家老屋敷の庭園。格式のある見事な庭園で、柳生家の品格が漂っていた。
泰山の古代遺跡探訪記topへ