京都から遥か北方にクルマを走らせ、王仁三郎の綾部を抜け、さらに走ること数十分で大江町につきます。
かの酒呑童子で有名な大江山です。綾部からの風景は山容がいかにも険しくなり、なるほどその昔は鬼が
出ると恐れられたのもうなずけます。以前より訪れたいと思っていた元伊勢をようやく訪れることができました。
大江町近隣には、元伊勢外宮の豊受神社と元伊勢内宮の皇大神社があり、その名の通り、現伊勢神宮の
元のという意味の非常に古い神社なのです。本命は内宮の本来のご神体である霊峰日室ヶ嶽です。
これこそがどうしても一度は直接見ておきたかったヒラミツトとしての聖山なのです。そしてそれは期待値を
遥かに超えた存在であり、現在でもまさしく生きている、スーパーパワーなのでした。その包み込むような
あたたかな霊気はまるで太陽のごとくであり、降雪時期にもかかわらず、私たちを照らしておりました。
日室とはよくぞなづけた名称であり、別名の岩戸山、城山よりは圧倒的に日室(ヒムロ)の響きがふさわしい
大いなる存在でした。霊気が香るという表現が最も適しているように感じます。そして日室ヶ嶽の描写を
より鮮明にお伝えするには、画像上ではどうしても音楽の助けが必要です。
今回のイメージサウンドを霊気の
香りとして知覚していただき、しばらく冒頭のイメージ写真をご覧頂いてから、本文に進まれますようお願いします。
写真からもその強烈なあたたかな霊的波動が伝わることと思います。日室ヶ嶽の存在ゆえに、この地に
元伊勢が存在しうる…と言いきっても過言ではありません。日本第一級のヒラミツトであると確信します。
1999 泰山記
2010 高精細画像に置換え+補足
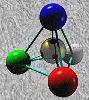 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.



















