六甲メガリスゾーンについては、甑岩の項で言及したように、阪急電鉄の駅4つ以上にまたがる広大なエリアだが、
急峻な六甲の地形がこうした状況を人々の眼から遠ざけている。
…
東側にある著名な甲山から西側の保久良神社までは東西にかなりの距離が在る。
岡本という小さな駅を降りて、線路を渡り、すぐに始まる神戸特有の上り坂を北に
上がる。
…
今回の目標はずばり保久良(ほくら)神社だ。保久良の巨石群は”その筋”にも知名度が低い。
六甲メガリスゾーンには”著名な物件”が多いせいもあるだろう。だが岡本駅に一旦降り立てば
「よほどの好き者でないと、わざわざ下車するにはいかにも目立たない場所だ!」…という実感が
そのことを納得させてくれる。
…
保久良は火座(ほ・くら)が語源的ルーツと言われている。甑岩の”蒸すような暑気”と通底する
「熱に関わる何か」が惹きつける。
…
保久良神社の裏手を北に小一時間も歩くと、知る人ぞ知る、カタカムナ文字研究の
楢崎皐月が、仙人;平十字(ヒラトウジ)に邂逅した金鳥山に行きつく。
…
金鳥山の更に奥には剣座(ツルギクラ)で有名なゴロゴロ岳があり、最終的には六甲山系に至る。
…
岡本周辺は芦屋の佇まいに似た風情の住宅である。その住宅街を縫う様に幅員の狭い坂道が
縦横に走っている。…果たして”こんなところに”本当に巨石群があるのだろうか…。
そのささやかな違和感が、いつもの”石探し感覚”を大きく狂わせていた。
…
道をわずか一本間違えて、そのまま30分もきつい坂道を北進してしまった。気付いたときには
すでに神戸市街地が眺望できる高さにまで来ていた。住人に尋ねると、「もうひとつ尾根を越えたところ」にあるという。
このままの標高でいけないものかと尋ねたら、「横断の道は無い」とすげない返事が返ってきた。
…
珍しく2時間ほどもロスをしながら、ようやく保久良神社への登り口を見つけ、つづら折れのだらだら坂を30分
ほど登ったところに、保久良がある。保久良の参道に入ってしまえば巨石の香りが漂い出す。
要するに、保久良神社は海岸線の岡本からいきなり200mの小高い山になっているのだ。
…
保久良は地元ではかなり位置付けの高い神社である。大祭(ダンジリで有名)もある。また日々参詣客が絶えないようだ。
そしてその格式は頂上の境内エリアに入った瞬間に得心が行く。保久良神社エリアは忽然とその重厚な
空気を現出させる。
…
まるで”巨石ヶ原”の様相を呈する保久良神社一体は構造体的には、北部にある金鳥山、ゴロゴロ岳に対して
拝殿的な位置付けに在ると考えられる。(未確認なので直観的な感想)
金鳥山に至る経路(古代参道)にシンボルらしき巨石があったり、金鳥山頂上に磐座が存在すれば保久良と
金鳥山は一体で考える必要があるだろう。
2001泰山記
2010 高精細画像に置換え+補足
今思い返すと、2時間ほどものタイムロスが逆に良かったと感じている。それは、おそらく2時間前に保久良神社に辿り着いていたのならば、保久良からそのまま北の金鳥山を目指して山中に入って行き、金鳥山中で夕暮れを迎えるはめになっていただろうと思われるからだ。保久良から金鳥への登山路は殆ど人通りがないせいか、道が荒れ、藪で前が見えないくらいなのである。時刻的には登山を諦めるに充分であった。次回行くときには、朝方から誰かと連れだって行くのが良いと思っている。保久良は単独ではなく、明らかに金鳥山と一体構造なす巨石ポイントであると考えている。
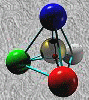 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.

























