Thank you for your access.or This page automaticaly jumps to PDF version in 10 sec. to.pdf-page Go!
|
全ての画像には著作権があります。画像の無断使用をお断りいたします。
Copyright(C) by Taizan 1996-2010
京都笠置山(きょうとかさぎやま)京都府相楽郡笠置町笠置山 標高290m
京都笠置山
Kasagiyama ; kyoto
E-mail to Taizan ; taizan@gainendesign.com
『泰山の古代遺跡探訪記』Topページ
泰山の古代遺跡探訪記
Presented by…
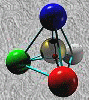 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.
※概念デザイン研究所FaceBook
※サイトオーナー泰山こと山口泰幸FaceBook
※ご連絡用メール;taizan@gainendesign.com
※概念デザイン研究所Fホームページ
※泰山の古代遺跡探訪記ホームページ
岐阜県の笠置山と同じ名前の山が京都の南外れにある。巨石累々たる京都の笠置山だ。
笠置山巨石群は笠置寺の領域ともなっている笠置山の山中にある。別の言い方をすれば、笠置山は
岩石山である。笠置山全域とその周辺の地質は、白亜紀後期(9700万年〜6500万年前)の珪長質深成岩類である。つまり花崗岩の山である。
巨岩の凄さでは第一級ということなので、関西出張の合間を見て琵琶湖辺りから南下し、
山に入った。
名神、京滋バイパス経由で南郷から府道を南に下り、国道163号線通称伊賀街道を東に折れて笠置に辿り着く。
笠置町は木津川沿いの風光明媚なところである。笠置大橋を渡り、府道笠置・山添線を少し行くと笠置山
登山口の看板が出てくる。それを笠置寺に向かって上ってゆく。
笠置山全体が笠置寺の境内になっているので、入場料を払わないと巨石が見れない仕掛けになっている。
寺の案内所で貰った笠置寺略記がこの山の特徴をよくあらわしているので、以下に紹介する。
なお、笠置寺は由緒のある寺で、天武天皇勅願所であり、後醍醐天皇行在所でもある。後醍醐天皇が笠置挙兵をこの地で行い、
南朝をスタートさせたのである。
-----『笠置寺栞』
笠置寺の創建は古い、すでに2000年前から笠置山の巨岩は信仰の対象となっていた、このことは笠置山の中心をなす
大岩石の前から弥生時代の有樋式石剣が発見されたことによってわかる、しかし実際に建物が建てられ人が住み着いたのは1300年前である。
1300年前東大寺の実忠和尚、その師良便僧正によって笠置山の大岩石に仏像が彫刻されその仏を中心として笠置山全体が一大修験行場として
栄えたのである。
平安時代永承7年(1052年)以降の世の末法思想のの流行とともに笠置寺の大磨崖仏は天人彫刻の仏として非常な信仰を受けたのである。
鎌倉時代建久2年(1191年)藤原貞慶(後の解脱上人)が日本の宗教改革者としてその運動を笠置寺から展開するとき笠置山は宗教の山、信仰の山
として全盛を極めた時であった。
しかし元弘元年(1331年)8月27日倒幕計画に失敗した後醍醐天皇を当寺に迎えたことにより攻防1ヶ月ついに笠置山は全山焼亡以降
室町時代少々の復興を見たが江戸中期より荒廃、ついに明治初年無住の寺となった。
明治9年丈英和尚狐狸の住む荒れ寺に住して笠置寺の復興につくすこと20年ようやく今日の姿となったのである。
-----
笠置山は紀伊半島のど真ん中に位置するいわゆる山奥にあるので、かなり近づかないとその全容はつかめない。
遠方からその姿を見るのは無理なのである。笠置大橋辺りから見上げるとようやく笠置山の容姿がおぼれながら
わかってくる。
笠置寺の案内所の掲げられている「笠置山寺全景」を見れば分かるように、笠置山の形状はまさにピラミッド型である。
そして人工加工痕跡を有するいくつかの巨石群を踏まえると、ピラミッド山の一つであると考えられる。
いずれにせよ、その巨石の大きさと美しさ、夥しさにおいてすこぶる印象深い山なのである。
参考資料;『ピラミッド山の具象構造と概念構造』
岩質に関する情報提供; 湯畑野秀明さん
探訪;2007年7〜9月 記;2008年1月 泰山

写真001
笠置山散策路の入り口に掲げられた「笠置山寺全景」図。笠置山がピラミッド型をしているのが明白である。
笠置寺から反時計回りで笠置山を周回するように散策路は続く。

写真002
散策路で最初に出会うのがこれ、弘法大師像と大師堂。大師堂の横を通り過ぎて奥へと入っていく。

写真003
正月堂に向かう。頭上にはオーバーハングした巨石。根元には苔むした岩が。

写真004
オーバーハングした巨岩の下方にある、「先端の平坦部」が特徴的な巨石。

写真005
オーバーハングしていた頭上に覆いかぶさるような巨石は船首のようでもある。これが薬師石。高さ12m。
後ろからやって来た父子連れの若いお父さんが、「ここはね、UFOの基地だっていう噂もあるんだよ!」と子供に
解説していたのが、微笑ましかった。

写真006
薬師石の根元。

写真007
弥勒大磨崖仏。観光的には最も有名な笠置山の岩石彫刻。
高さ20mの巨岩に15mの高さの弥勒像が彫られている。1ショットでは入りきれないほど大きい。
平安時代に大陸から呼び寄せた渡来人によって彫られたという。これまで三度の御堂焼失により
壁面の彫像が崩壊したそうだ。しかしながらその存在感は今なお大きなものがある。

写真008
十三重石塔(重要文化財)。石塔の後方が高さ7mの文殊石。

写真009
千手窟。実忠和尚が雨乞いの修法を執り行ったとされる陰の空間。

写真010
正月堂を過ぎると岩の上を歩くように散策路は続く。やがて藤原期に彫られた傑作の虚空像坐像がある巨石が出現する。

写真011
散策路から正月堂を振り返ったところ。…そこにも巨石の壁が。

写真012
磨崖仏(虚空像仏)。仏像もさることながら、この岩の下には若干休めるところがあり、
そこで佇むとすこぶる気持ちが良いのである。

写真013
胎内くぐり(行場入りのための清めのトンネル)。笠置山には滝が無いので、この空間を通ることで
身を清めた。

写真014
胎内くぐり内部の天井石。安政地震で天井の巨石が落下したために、その後石板で天井を形成している。

写真015
胎内くぐりの出口側から見たトンネルの構造。

写真016
ドルメン状の巨石。

写真017
太鼓石(たたくと音がする)。

写真018
巨石の組み合わせによるトンネル構造。

写真019
そのトンネル構造の天井石の表面。典型的な花崗岩である。美しい。

写真020
眼下に流れる木津川。実におだやかで風光明媚なのである。

写真021
ゆるぎ石。右側。戦乱時に落とす目的で置かれた石とか…ちょっと動かそうとしてみたが、びくともしなかった。

写真022
ゆるぎ石付近からも絶景が眺められる。

写真023
平等石。眺めが素晴らしい。江戸時代は月見の場所だったとか。

写真024
頂上付近にある巨石。下部にこの巨石の支え構造が見える。支え構造自体は近年のものかも
しれないが、この巨石を明らかに「その姿勢に保つ」意図が見える。そこがポイントになるだろう。

写真025
前の巨石と似ているが別の巨石で、この傾斜角も前者と近い。この巨石の特徴はその下にある
陰の空間である。陰の空間をあえてここで形成しているようだ。実際にこの中に入ると空間が変化するように感じる。

写真026
頂上に向かうルートの狭隘部分。山城として使ったときの名残か…。

写真027
形状が牡丹餅のようでユニークな巨石。下部に支え構造がある。

写真028
頂上付近。この手の巨石がごろごろしている。

写真029
後醍醐天皇行在所跡。私とっては碑文がはめ込まれたこの巨石の方が気になるところ…。

写真030
大師堂裏手の巨石。山を一周して降りてくると、最後に出てくるのが大師堂。
泰山の古代遺跡探訪記topへ