山梨の下石森から笛吹川を渡り、雁坂道を塩山の方面に向かうとやがて
左かたに「←大石山」という看板が目に入ります。
大石神社の巨石は是非とも見たかったものです。
「大石山」とあるからには、これも巨石だけではなく、石森山や鮒岩の丸山
と同じようにある種の小高い山になっているのだろうと予想しながら、
脇道を人家の少なくなるほうへ進みます。近隣には「岩手小学校」の文字が。
”岩手”が甲府にもあるとは興味深いものだ…と感じつつ、さらにクルマで
走ること5分、左手に青青と樹木の茂った小高い山が見えてきます。
巨石の山はなぜにこうも直ぐに分かるのだろうか…。巨石の周囲は樹木が
成長するという話がありますが、確かに巨石群には緑濃き樹林が付き物です。
やがて大石神社の鳥居の前に立つと、天空にも昇るばかりの参道の階段が
見えます。
やはり大石山は巨石を配する丘なのです。
果たして、大石山の頂上で私は超巨大な球体巨石を目の当たりにするのでした。
今まで日本中を歩いて来ましたが、これほど超巨大な球体状の巨岩を見るのは
初めてです。そのあまりの大きさに思わず笑ってしまうほどなのです。
大石神社のご神体であるこの超巨石は「浮舟石」となずけられていますが、
残念ながらこれも分断された痕跡があります。さらにそれを近世に石工が
楔で欠いた跡もあります。もとを辿れば超巨大な太陽石であったと思われる
この大岩は古代にすざまじいエネルギーを放出していたに違いありません。
巨石に一礼し、その頂上に立つと、いまだにその過去の栄光がじんわりと
伝わって来ます。あまりの大きさはカメラに収まり切らないほどです。
大石山は背後に聖山;帯那山を配し、東南に塩の山、そして富士山を望む
素晴らしいイヤシロチ上にあります。行って、見て、そしてその存在感を感じて下さい。
1997泰山記
2010 高精細画像に置換え+補足
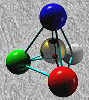 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.



























