in Kumamoto Pref. / Giga Rock tower : Fudougan
Copyright(C) by Taizan 1996-2010
E-mail to Taizan ; taizan@gainendesign.com
『泰山の古代遺跡探訪記』Topページ
阿蘇外輪山にある押戸ノ石巨石群については2003年に広島在住の知人から探訪記を投稿してもらっていたので情報は良く知っていた。今回、九州の神社巡りの途中、
せっかくの機会なので、天岩戸神社から宇佐神宮へ回る途中、直接巨石遺構を探訪しに行った。押戸ノ石丘は本当によいところで、一日中ぼんやりとここで過ごしていても
よいほどの素晴らしい場所である。場所的には阿蘇五岳の北、大観峰のさらに外側のマウンドの連なる地帯に存在する。ふと大噴火以前の巨大阿蘇をイメージしてみると
押戸ノ石丘周辺が山麓になる超巨大な富士山型の噴火山であり、その姿はさぞ威容であったことだろうと思う。
阿蘇の外輪山を越えて国道212号線を北上すること数Kmで左側に「マゼノ・ミステリーロード」に折れる分岐点がくる。そこを左折し5分くらい走ると渓谷の橋の手前をさらに
左に折れる小道がある。現在ではここも舗装されている。是非論はあろうが日本は本当に山奥まで舗装路があり、ドライブ好きにとってはありがたいことである。
因みに、「マゼノ・ミステリーロード」のマゼノとは馬の背のことだそうだ。地形が馬の背に似ていることからこの辺りをマゼノというのだが、先述の橋の辺りが
マゼノ渓谷となっている。そのマゼノ周辺に今回探訪した「押戸ノ石」という巨石遺構があることから「マゼノ・ミステリーロード」という名がついたそうだ。
押戸橋の入り口からさらにもう少し舗装路を走るとさらに分岐路があり、そこを左に折れ砂利道へと進んでいく。ここで右に折れると景勝;マゼノ渓谷に出る。愛車のマスタングだとおそらく側溝にタイヤを落とすほどの狭い道。
小型のレンタカーが幸いしてくれた。それでも対向車が来たら…どうするのかなあ…などと独りごとをいいながら、行ける所までクルマで行く。幸い、ウイークデーの夕方だったので
対向車も無く、助手席の家内の愚痴を除けば、なかなか気持ちの良い山道だった。分岐路から数分で、無人の小屋があり、そこを右に折れてさらに5分程度道なりに走ると広場に出てきた。
そこが駐車スペースになっている。なんと先客が2台もいるではないか。いやはや休日の昼頃だったなら込み合っていたに違いない。
駐車場からはさすがに徒歩での登坂となる、駐車場からは押戸ノ石巨石は全く見えないので、風邪気味の家内はあとちょっとの登りにげんなり顔をする。そういう連れをダマシダマシ登ったので頂上に着くのに、かれこれ20分近くも
掛ってしまった。ここが押戸ノ石丘と呼ばれる標高845mのマウンドである。その頂上部に代表的で最も大きな三角形をした巨石が鎮座している。
心地よくも、たしかに不思議な光景である。牧草地帯が延々と続くマウンド群に囲まれたところで、大きな樹木はなく360度の眺望が得られる。
南に阿蘇五岳、東に九重連山を望み見渡す限りの草原なのだ。その一角、この押戸ノ石丘の頂上部分にだけ巨石群がある。
押戸ノ石巨石群の岩質は主に安山岩からできているそうだ。また阿蘇の火山活動によって堆積した凝灰岩や溶結凝灰岩によって周辺のマウンドは造られているようだが、比較的硬い安山岩が
浸食作用に打ち勝って、押戸ノ石巨石群の現在のような形態になったであろうと考察されている。この辺は専門家の情報コチラがたいへん参考になると思う。
感覚的には押戸ノ石巨石群の存在は私には人為を感じさせて止まない。完全なる自然現象による浸食作用だけで、ここだけに巨石が残るかどうか、地質学者ではないのであくまでも感覚なのだが、見渡す限り草原のマウンド群の中で
ここだけに巨石群があることになんらかの人為的な企図を感じざるを得ない。巨石遺構の中には明らかにその巨石がある山の組成とは異なる(例えば堆積岩の山の頂上に花崗岩の巨石の石組があるなどの例)巨石が存在しているが、
押戸ノ石の巨石をどこからか持ち運んだということはないだろう。やはり天然に存在する安山岩を利用しつつそこに意思を含めて残存させたというほうが理解しやすいと思う。
小生は出身がエンジニアなので、つい工学的な視点で巨石遺構を見てしまうが、現在であっても古代であっても、もしそこに人為を介在させるのならば、最も効果的で、最も造営に効率的な道を選択すると思うからだ。
だから、基本的に巨石遺構造営には、『そこにある自然物』を最大活用する…ということが重要なポイントなのであると思う。「日本ピラミッド」論の著者;酒井勝軍も同じことを言っているが、「なるべく自然の山や石をそのまま活用する方がよい」
というのが超古代巨石構造物の基本姿勢であると思うからだ。
人為的な作用の中で天然石に人工を加える行為として、直接対象となる天然石に手を入れるということと同時に、対象物以外を”片づける、整理してどかす、粉砕する”ということも大いに考えられる。
例えば、与那国島海底遺跡の回廊状の通路からは石の残渣が取り除かれていると言われているし、兵庫県の生石神社の石の宝殿の残渣は隣の岩石山に片付けられている。こうしたことからも
押戸ノ石巨石群は天然なれど、重要な巨石だけ残し、若干の手入れと整理をした可能性もある。岐阜県にある岩屋岩陰遺跡で見た巨石配列のように、古代人(今の我々の祖先ではないかもしれないが)の叡智と
芸術的センスは測り知れないものがあると感じている。
押戸ノ石巨石群は「ストーンサークル」と「ペトログラフ/ペトログリフ=線刻画」でつとに有名だし、地元でもこのブランドに力を入れているようなので、水をさすつもりは毛頭ないのだが、それでも一応古代遺跡探究家と
自称しているので、客観的な所見も述べておきたい。
押戸ノ石巨石群には明らかに人為を感じるものの、実は現地探索した結果、個人的には明確な「ストーンサークル;複数の列石が円環状の形を形成し、中央に何らかの中心巨石があるような…」といえる印象に残る巨石遺構は見えなかった。2か所ほど直径2〜3m程度の小さなサークル的なものも含め、意味のありそうな直列構造や形態、方向性は認識できたが、”ストーンサークル遺跡”といえるほどのストーンサークルは認識できなかった。
またいわゆる「ペトログラフ/ペトログリフ」であるが、ライン状の線刻や盃状穴と言われる凹型の小さな穴はいくつも見受けられたが、文字を感じさせる痕跡は見えなかった。これは私が個人的に言語の一環としての”文字表記”を
巨石遺構の重要な構成要素と認識していないからかもしれない。”文字表記”以前の概念表徴としてのカタチや配列等による表紀の方が永続性と訴求力とにおいて圧倒的に優れているからと、私は勝手に妄想しているのである。
また、花崗岩も含め、岩石はイメージよりも柔らかいというか脆いところがあって、7〜8年で結構風化作用を受けるという研究結果もある。従って数万年の時間経過を想定していると考えられる巨石遺構の表層に文字を表記して残すのは
あまり得策ではないように思える。とくに押戸ノ石巨石群のような丸裸の山頂部に風雨に直接さらされる環境において、岩の表面にわずかな切り込みを入れておくというのは造営趣旨からはやや疑問でもある。数万年単位の時間経過を
想定すると考えられる巨石遺構の造営基本コンセプトは、「個々の巨石の形状」、「個々の巨石の方向性」、「巨石間の関係性」、「巨石群全体の配置や構成性」、「巨石群から読み取れるストーリー性」などである思う。それらは
優れて超長期間の風雪に耐えうるからだ。
巨石上に明らかに文字が彫りこまれた例は確かにある。漢字、梵字、サンカ文字やアヒルクサ文字などの古代文字と言われるようなもの、あるいは絵のようなもの、などであるが、表面への削りこみというのは風雪に晒されれば
永くても数千年が耐久限度ではなかろうか。従ってよりはっきりとした岩刻文字や絵画というものは巨石遺構の存在に対してかなり若い(最近という意味;最近と言っても数千年だが)痕跡と見るのが妥当であると思われる。
表層の文字表記がなくとも十分に巨石遺構はその意味性を表明できると考えてよいのではないだろうか。巨石(群や遺構、P山;ピラミッド山構造体)はあるだけで『無言に語れる』のである。
ちなみに、押戸ノ石巨石群はマゼノ渓谷近くの押戸石山(と呼ばれる)山頂部に並ぶもので、平面距離は全長約100m、全体が並んでいる方向はほぼ北東で、山頂部に向かうこのラインを追うと、小国富士と呼ばれる美しい形の
涌蓋山(わいたさん)、さらには国東半島付け根にある由布岳に至る。
結論的には…総合的に考察してみて、私は押戸ノ石巨石群は全体として祭祀施設であると思う。全部で百以上にも及ぶ大中小の巨石たちには全て役割が付与されているように思えた。そして必要ではない岩塊は整理され、片づけられて
この押戸山に現在ある巨石群のみが際立て残存できるようにした…と考えている。マゼノ渓谷(コチラを参照)を見れば分かるようにこの地帯は全域で岩石地帯である。それが草原状に整理され、押戸ノ石巨石群のみが設置され(残され)、周辺に樹林が殆どないことを考えると、人為が加わった良くできた祭祀施設であると思える。
ピラミッド山構造体を探究する私としては、ここが祭祀施設のある拝殿山と考えたいのだが、その御神体なる聖山の確定が、候補がいくつもあって判断しにくいので、P山構造体であるかどうかの考察は今後楽しみながら
してゆきたいと思うしだいである。
補足説明;文章中、まことに勝手ながら便宜上個々の巨石に”仮称”をつけさせて頂いた。現地で既に通称になっているものはそのまま使い、ネット上で多少なりともある呼ばれた方をしてるものはそれを使い、それ以外は形態的、機能的な側面を重視して
分かりやすくするために、”仮称”しているので、悪しからずご了承下さい。なお、下記の巨石群配置平面図は各種参考写真や当日の記憶をたどって作成したもので、かなり精確であるので皆様方の研究の参考にして頂ければ幸甚である。
2012年春 泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|
押戸ノ石の所在地;
熊本県阿蘇郡南小国町大字中原地区湯風呂;押戸ノ石丘 
北緯:33.031326、東経:131.050758;押戸ノ石巨石群の頂上部三角石の衛星写真による位置

これが押戸ノ石巨石群の中の最大級で最も代表的な巨石である。以前はこの巨石に注連縄が張ってあったこともある。地元でも明確にこの石に命名されてはいないようだ。従って勝手ながら便宜上”頂上三角石”とよばせて頂きたい。
高さ5.5m、周囲の最大長15.3m。
遠方右手に見えるのが小国小富士と呼ばれる涌蓋山(わいたさん)1499.5m。九重連山の北端にある。押戸ノ石にとって涌蓋山とは重要な聖山である思われる。
”頂上三角石”の頂上部は涌蓋山を意識して成形されているように思える。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

同じく”頂上三角石”の別のビュー。今度は涌蓋山を左に、九重連山を右に見ている。このの方角の遥か遠方100数十Kmの処に霊峰;由布岳がある。
このビューで重要なことは”頂上三角石”の頂点が、この角度から見ると双頭になっていることである。私はこの切り込みで形成された双頭部分は
人為的な意図が含まれると感じている。因みに押戸ノ石の北東に由布岳はある。涌蓋山も北東、東が九重連山、阿蘇中岳はほぼ真南に来る。ほぼ真西に
山鹿市の不動岩がくる。巨石には複数の表徴が施される場合があるが、涌蓋山と共に遥か遠方の由布岳にも意識が向いていることは否めない。由布岳は
押戸石山から百数十Kmなので、横浜から富士山を仰ぎ見るようなものである。ただし由布岳本体の確認はできなかった。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

上記写真で撮影した”頂上三角石”の反対側。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

3月12日午後4時頃の太陽を浴びる押戸ノ石。右が”頂上三角石”、説明看板の左が”筍石”、手前左が”方向石”、稜線上には”亀石”も見える。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

”頂上三角石”の南側にある巨石で、重要なことはこの巨石が阿蘇中岳(噴煙を上げている)に向かっているということ。この巨石は
”頂上三角石”に次いで(個人的には)最重要の巨石で、「拝ヶ石巨石群」の項でも説明したが、これもまさに聖山としての中岳頂上指し示す
”方向石”あるいは”指頂石”であって、形態的には”男根石”である。最も重要な認識は、押戸ノ石巨石群は聖山として阿蘇中岳を拝謁している
ということである。この視点でいうならば、押戸ノ石巨石群は阿蘇の拝殿構造にあたるといえる。この巨石は特徴として、押戸ノ石巨石群の他の石と
異なって、「斜めに設置」されている感がある。そこに巨石遺構としての意味と証左が残されていると思うわけである。
因みに巨石の背筋の方向はほぼ真南をさす。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

これが”方向石”の背筋部分。こうしてみると”亀石”という側面もあるのかもしれない。巨石の中には”人面”と”龍頭”とを兼備するものなども
よくあるので。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

南小国町教育委員会作成の説明板。こうして地元で大切に保存されることは極めて重要なことである。小国町の皆さんの
ご努力に頭が下がる。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

押戸ノ石巨石群をかなり精確に作成した全体配置図である。作成するのに苦労をした。主だった巨石には”仮称”を付し、分かりやすくした。現地でも用いられている、巨石群への「参道」から入り、いくつかのグループに分けられた
巨石群を順次たどって行くと約100m先の山頂部に、最も重要な”頂上三角石”がある。巨石群はほぼ北東の方向に沿って存在し、この全体図からも何らかの人為的な意図を感じることができるだろう。この図と照らし合わせながら、
以下の個別の写真と文章をお楽しみいただきたい。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

九重連山を背景に”頂上三角石”、”方向石”、その手前に”第一列石”、一番手前が”筍石”。”頂上三角石”と”筍石”とを結ぶのが稜線となる。このライン上に
順次”亀石”、”祭壇石”と続く。”第一列石”は4個の石が並び、その先頭部はかなり大きめで、仮称”冠石”と呼んでみた。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

南西方向に稜線を下って行き、”祭壇石”を過ぎて、西方向をみたところ。右の二つが親子の”オットセイ石”、その左隣(奥)が”陰陽石(群)”、その手前に”小サークル”があり、
左手前の大きめの石が”台石”、その奥の尖ったのが”つつじ石グループ”の”桃太郎石”。ここはひとつの大きなグループをなしている。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

形態的には『蛙石』あるいは『蛇石』という方が相応しい、通称”祭壇石”。右が”オムスビ石”
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

親子の”オットセイ石”を北方向にみたところ。この鋭角部分が特徴的。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

最も低い位置にある、”挟み石;男女石;陰陽石”の手前にある”参道岩塊”
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

これが”挟み石;男女石;陰陽石”。横から撮影。サイズ比較のため人物を入れておいた。比較的大きな巨石グループで、2枚の巨石の隙間を抜ける。
2枚の巨石が陰石を示し、手前の大ぶりの石が陽石を示す…とされている。右手は”小サークル”の一部。
”挟み石;男女石;陰陽石”の2枚の巨石の隙間から北東方向、すなわち稜線上を山頂に向かって覗くと、まずは”祭壇石”が、その後方に”頂上三角石”が見える。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

”小サークル”を少し山頂側に行くと、サークルっぽい”つつじ石グループ”になる。つつじが咲くので。そのグループの一つが
比較的大ぶりで、頭頂部が二つに割れている”桃太郎石”、少し見えている。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

”祭壇石”から”オムスビ石”を南方向にみたところ。遠方には噴煙を吹く阿蘇中岳が見える。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

”祭壇石”を単独で北方向に撮影したもの。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

”方向石”隣の”第一列石”の頭頂部に相当する”冠石”。次いで、2番目と3番目の列石が見えている。”第一列石”は4個の石が並ぶ。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

最長の特徴ある”第二列石”で6個が並ぶ。完全な直線ではない。最前の巨石にはいくつもの盃状穴がある。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

同じく”第二列石”。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

”オムスビ石”頭頂部の石越に阿蘇根子岳。”オムスビ石”は大きめの巨石2個といくつかの小さめの石で形成される集団で、
”祭壇石”の南側にある。ちなみに、”祭壇石”の北側には、山容麗しい「渡神岳;とがみだけ」が来る。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

”筍石”越に、”亀石”を右手に、”オムスビ石”とそれに隠れた”祭壇石”を、西方向に見る。”筍石”と”亀石”、さらに”祭壇石”の間は比較的あいている。
集団的には、”参道岩塊”、”陰陽石”集団、”オットセイ石”、”つつじ石”集団、”祭壇石”、”オムスビ石”集団、”頂上三角石”、”方向石”集団の4集団があり、
”亀石”、”筍石”は距離を置きながら、単独で存在している。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

南方向の阿蘇五岳を望む。なんとも絶景過ぎて、ため息が出る。白い噴煙を吹くのが中岳。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

240度のパノラマ。左から、涌蓋山、九重連山、遠くかすかに見える祖母山系、阿蘇五岳。いや〜なんとも絶景!
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

上記パノラマ写真の説明。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|

約1時間の探訪を終えて、名残惜しさをこらえながら来た道を駐車スペースへと戻る。あれが駐車スペースとクルマ。帰る頃には先客の1台が既に帰路についていた。
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
|
泰山の古代遺跡探訪記topへ
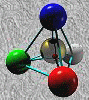 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.


























