Thank you for your access.or This page automaticaly jumps to PDF version in 10 sec. to.pdf-page Go!
|
全ての画像には著作権があります。画像の無断使用をお断りいたします。
Copyright(C) by Taizan 1996-2010
砥鹿神社奥宮(とがじんじゃおくみや) 愛知県豊川市上長山町本宮下4
砥鹿神社奥宮
Togajinjya-Okumiya ; aichi
E-mail to Taizan ; taizan@gainendesign.com
『泰山の古代遺跡探訪記』Topページ
泰山の古代遺跡探訪記
Presented by…
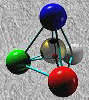 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.
※概念デザイン研究所FaceBook
※サイトオーナー泰山こと山口泰幸FaceBook
※ご連絡用メール;taizan@gainendesign.com
※概念デザイン研究所Fホームページ
※泰山の古代遺跡探訪記ホームページ
愛知県の豊川沿いも巨石群の宝庫である。ピラミッド山ではないかとされている石巻山、照山、砥神山と並んで本宮山789mも美しい山容の大ピラミッド山と考えられる。
本宮山の頂上付近には砥鹿神社の奥宮があって珍しい社や特徴的な磐座がいくつもある。砥鹿神社奥宮はその昔ここが唯一の砥鹿神社であったらしい。奥宮から少し離れたところに
国見岩という巨大な磐座があり、その根元の陰の空間には天の岩戸神社が祀られている。ここでは、奥宮周辺の巨石群について言及してみたい。
本宮山の頂上には大きな駐車場と公園があり、その中に本宮山についての記載がある。まずはその全文を掲載することにしよう。
『飛鳥時代の大宝年中(七〇一〜七〇四)文武天皇の病気のため、煙厳山(鳳来寺山)に住む勝岳仙人を迎える勅使として来られた草鹿砥公宣卿(くさかどきんのぶきょう)が、
当地にて道に迷われたときに、童子が忽然と卿の前に姿を現し、煙厳山を教えたという故事がある。
一方、鹿は古来、我国では神に仕える動物として親しまれている。当地域は、本県における鹿の生息地で、現在でも時折野生鹿の姿を見ることが出来る。
本宮山は、東海道筋から分岐して奥三河へ向かう道程において、目標となる山であり、また、限りない自然の恵みをもたらす山として、地域の人々に
あがめられてきた霊峰である』
本宮山山頂には、草鹿砥公宣卿が創建したものと伝わっている砥鹿神社の奥宮がまつられている。御祭神は大己貴命
(おおなむちのみこと)で延喜式(えんぎしき)の中にも記載されている古社である。三河一宮でもある。
本宮山;砥鹿神社奥宮は三河湾に注ぐ豊川沿いにある。豊橋、豊川あたりからこの周辺最高峰の本宮山の秀麗な姿はどこからでも拝める。
豊川から国道151号線を東北方向に進み、国道301号線とぶつかるところで左折し、山へと登ってゆく。
現在は無料となっている本宮山スカイラインへと進むとスカイラインの終点が山頂となる。
かなり広い駐車場、頂上公園、山頂に林立した電波塔が目に飛び込んでくる。
果たしてこんなところに磐座などがあるのだろうかと…一瞬考え込んでしまうような近代的風景ではある。
三河周辺の航空写真。海岸線が奥まで進行していた頃には本宮山も「水際」にあることがわかる。
また、石巻山、照山とは一直線上にあり、これらの山と深い関係があることが想像される。

頂上公園内の「みちのり」の像
参考資料;『ピラミッド山の具象構造と概念構造』
探訪;2007年7〜9月 記;2007年11月 泰山

写真001
砥鹿神社里宮の拝殿。
砥鹿神社は大己貴命(おおなむちのみこと)=大国主を祀る旧国幣小社で東海地方の総鎮守。
本宮山に祀られていたが、今から約1300年前にこの地に里宮が建立された。
この里宮と本宮山奥宮の二社をもって三河国一宮とされている。

写真002
砥鹿神社境内の『神亀石』

写真003
『神亀石』の表面紋様

写真004
砥鹿神社の御神紋である「亀(六角形)の中に卜(ぼく)」のマーク。

写真005
遠方に聳えるのが本宮山。なだらかではあるが美しいピラミッド状の山容である。
この姿が豊橋、豊川付近からよく見える。
写真は石巻山山頂から撮影したもので、ちょうど中間地点に小型ピラミッド山の”照山”が見える。

写真006
本宮山の山頂駐車場から5分ほど来た道をもどる方向に進むと、やがて砥鹿神社奥宮の巨大な赤い鳥居が出現する。

写真007
そこからさらに数分歩いたところに渋い感じの石の鳥居がある。この辺から急速に空気が変化してくるのがわかる。

写真008
石の鳥居から奥宮へ向かう参道の脇には、いつもながらの異形の樹木が生えている。
こうした樹木を見れば、奥宮のある場所のパワーが強いことを感じることができるのである。

写真009
3本杉。真ん中の杉が日の光を浴びて黄金色に輝いていたのが印象的だった。

写真010
樹齢1000年と言われる杉の御神木。高さ65m、周長30m。迫力が凄い!

写真011
「御福釜」;熱湯の中に手を入れて正邪を判定するとか…

写真012
奥宮のすぐ傍に「富士山遥拝所」がある。この方向に静岡の富士山が見えるのである。

写真013
砥鹿神社奥宮の由緒書。
御祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)=大国主命。2月6日に例祭がある。また
10月14日には境内摂社である荒羽々気(アラハバキ)神社の例祭も執り行われている。

写真014
これが砥鹿神社奥宮の拝殿である。明るい感じの爽やかな社殿であった。

写真015
奥宮の東側はすぐに急階段になっている。この参道上にいくつもの巨石がある。
これもそのひとつ。小生の持論である「巨石は樹木を育てる」に相応しい光景。

写真016
さらに下ると向こうに小さな社が見えてくる。その前に、きれいな平滑面を呈する巨石がある。

写真017
これはさらに下がった所にある巨石で、写真16の巨石と似ているが別モノ。

写真018
八柱神社;「湍津姫命、市杵嶋姫命、天忍穗耳命、天穗日命、天津彦根命、活津彦根命、熊野?樟日命、田心姫命」 を祀っている。

写真019
八柱神社を過ぎるとさらに石畳状の岩盤によって形成された参道が続く。

写真020
かなり下ったところに荒羽々気神社が現れる。

写真021
荒羽々気神社から20mほど下ったところに『天の磐座』がある。

写真022
この『天の磐座』は荒羽々気神社もあることを考えると古代の重要な施設であったと想像できるが、
参道自体がこの『天の磐座』の真上を通るようになっているのが気にかかる。

写真023
麓から登ってくるときにくぐるのがこの鳥居。今回は逆に降りてきた。
ここからあらためて奥宮へと戻った。

写真024
実は先ほどの八柱神社の裏側(登ってゆけば表)はこのような対になった巨石の石門になっている。
この石門構造は重要であると考えている。石門の上部には必ず重要な磐座があるはずなので、
おそらくは奥宮社殿の下あたりに磐座が埋もれているのではなかろうか。
それならば、社殿近くの御神木杉の巨大さも凄さも理解ができる。

写真025
本宮山頂上は奥宮のあるところからは数百mほど離れている。その頂上付近から奥宮のある東南方向の
小高いピークを撮影したところ。写真のこんもりした緑の中に奥宮社殿がある。

写真026
本宮山頂上789m部の状況。電波塔が乱立していて、奥宮の風情のかけらもない。
豊橋、豊川あたりから見える山頂はこの部分にあたる。アンテナのある山頂には今は
何も見つからない状況である。近代的な設備が建てられるとき、おうおうにしてそこにある
重要な巨石などが掘り返されて破棄される可能性が高い。本来ならばこの山頂部分にも顕著な
磐座があってしかるべきかと思うのだが…
泰山の古代遺跡探訪記topへ