Thank you for your access.or This page automaticaly jumps to PDF version in 10 sec. to.pdf-page Go!
|
不動岩探訪記2012;熊本県
in Kumamoto Pref. / Giga Rock tower : Fudougan
Copyright(C) by Taizan 1996-2014
ーーーーーー
出口聖師とは大本教の出口王仁三郎(でぐちおにざぶろう、わにざぶろう;因みに私は明治生まれの父から当時ワニザブロウと言っていたと聞いていた)のこと。
2012年春 泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
不動岩の所在地;
〒8610522 熊本県山鹿市三玉地区蒲生 556-25
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
2012年泰山記:Copyright (C) 2012 by Taizan
E-mail to Taizan ; taizan@ainendesign.com
『泰山の古代遺跡探訪記』Topページ
泰山の古代遺跡探訪記
Presented by…
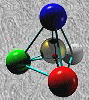 Gainendesign-Labo.
Gainendesign-Labo.
熊本へは4回目となる、10数年ぶりの訪問である。熊本を含む九州の中央から北部に対して、何故だが「精神的なゲート」がこの春に開かれたような気がしたので、
これまで気にはなっていたが、なかなか腰が重かったポイントを探訪して来た。アクセスとしてはそれほど気軽には行けない、山鹿市の不動岩(ふどうがん)である。
呼称についてはふどうがん、ふどういわの両方が使われているが、以前から慣れ親しんでいるふどうがんという呼称で通したい。
不動岩を知ったのは1990年。酒井勝軍の神秘の日本という書籍を刊行している”八幡書店”から、私が神秘の日本全巻を購入していたこともあって、”八幡書店ニュース”という
小冊子が送られてきた。その表紙に日本ではあまり見たことも無い岩石山の写真が掲載されていて、それが不動岩と言う物であることを初めて知ったのである。
その表紙を切り抜いてずっと保管していた。それはその表紙の解説が興味深かったからである。ちなみに、22年前に書かれた不動岩の紹介文章を載せておく。
出典は『八幡書店ニュースNo.19平成2年7月15日発行』。
《美山彦の造った神岩》
熊本県山鹿市の不動岩を、出口聖師は、美山彦(言霊彦)がロッキー山に造った神岩に相応すると説示された。ロッキー山の神岩等について、詳しくは
『霊界物語』第2巻3章を参照されたい。
山鹿市の菊池川流域は、トンカラリンなどの謎の遺跡とともに、装飾古墳が密集するエソテリック・ベルトとして
知られる。また、きわめて興味深いことに、これらの古墳に見られる壁画のモチーフは、ホピ族など北米インディアンのそれと共通する。
ーーーーーー
霊界物語とは同氏のトランス状態における口述筆記であり膨大な量に及ぶ。またここで言及されている北米ロッキー山というのは最近パワースポットとしてつとに
有名になってきている「セドナ」のことであり、ここはインディアンの居留地区にもなっている。ロッキーの神岩とは
コチラで紹介されているような山のことを指すのだろう。
Cathedral-rock-Sedona-Arizona
thanks for free-desktop-backgrounds.net
トンカラリンとは狭い通路によって構成される不思議な空間のこと、装飾古墳とはオブサン、チプサンの古墳群のことで、チプサン古墳の壁画は次の写真のような
ものである。
不動岩の生成と岩質は概略次のようになる。すなわち、
標高389mの山の中腹から頂上に掛けて3つの巨大岩塔がある。最前列の最大岩塔は高さ80m、根回り周長100m。
岩質は5億年以上前の古生代オルドビス紀の変斑糲岩(へんはんれいがん)で、それが浸食作用で礫岩になり海底で高圧縮された堆積岩。いわゆる”さざれ石”。
詳しくは
山鹿探訪ナビを参照下さい。
不動岩はピラミッド山に付帯するような巨石ではない。あくまでも巨大岩塔である。しかしそのいわれや伝説が面白く、また巨大岩塔がすべて”さざれ石の巌”であることも
興味深い。岩塔の真下には不動明王を祭る社もあり、山の麓には金毘羅神社もある。神岩としてご覧いただければ幸甚である。不動岩直下まで登れば、そこには絶景が広がり、
また春には桜が満開となる、場所として素晴らしいところである。

山鹿市役所前の国道325号線を東へ走り、約4Kmほどのところを来民小学校手前で左に折れ、県道197号線を3Kmほど北西に行ったところで、やがて右前方に不動岩を抱える岩石山が見えてくる。
標高389mの小山のちょうど中腹からにょきりと3本の岩塔が屹立している。前から前不動、中不動、後不動という。

県道197号線沿いに、金毘羅神社大きな石の鳥居があり、そこからが参道になっていて、そこから約1Kmで山麓に至る。
山麓にも金毘羅神社の第二の鳥居がある。この鳥居越しに見える不動岩の光景はなかなかいいものである。

不動岩〜蒲生池までは3.1kmのほどよい散策路になっている。この周辺は九州自然歩道(史跡探索コース)となっている。

第二鳥居へ向かう途中で不動岩を見る。なかなかの圧巻。第1の岩塔である前不動が迫ってくる。

さらに不動岩に近づく。

第二鳥居のところにある不動岩周辺の案内図。現在地点は第二鳥居。そのまま直進すると金毘羅神社の本殿に至る。
ここで右側の細い道路をクルマで上がって行く。岩塔直下までクルマで行くことができるが、クルマ1台分の細い道で
スリルがある。駐車場には数台の車を止められる。途中まではなんとマイクロバスも行くそうだ。たぶん桜の名所なんでしょう。

金毘羅神社の第二鳥居。ここからも勿論不動岩の雄姿が拝める。

クルマで10分ほどは登り、ようやく岩塔直下の駐車場に到着。これが高さ80mの不動岩の最前の岩塔。最前の岩塔を前不動という。一応サイズ比較のために
人物も入れておいた。

不動岩直下の社から不動岩を見上げたところ。実際の迫力はハンパなく凄い!しかも大きい。…ので、写真は3枚重ねと
なった。

不動岩直下の不動明王を祭る神社。平安時代(約1000年前)に山伏たちが修業のためにここに不動明王を祭ったのが
社の始まりとのこと。不動岩のなまえの由来も不動明王からきているとのこと。

不動岩から南西方向の熊本平野の眺望。素晴らしい絶景である。空気が澄んでいれば、不動岩の東南東に阿蘇山、南西遥か洋上に雲仙普賢岳、南南西に金峰山が見える。
…ということは拝ヶ石巨石群は金峰山と不動岩のライン上に来ることになる。拝ヶ石巨石群についてはコチラから

「みいくさの 神の姿を仰ぐかな 平伏す岩は まつろえる神」 という古歌が記された説明板。
この説明板でははっきりと『FUDOGAN』と書いてある。

不動岩、雲岳、彦岳の三岳を山鹿市三岳という。それにまつわる伝説の説明板。ここで言われている首石岩というのが
不動岩の南約1kmにある蜜柑畑の中にある。

先述のように不動岩はさざれ石である。実際の表面はこのようになっている。大小様々な礫がランダムに固まっている。

前不動の横からさらに登山路があって、不動岩の上まで行ける。これは前不動の裏側に回って前不動の後ろ姿を撮影したもの。

不動岩は前不動、中不動、後不動と3つの岩塔からなるが、この写真は左が前不動、右の細い岩塔とその直後の丸い岩は
セットで中不動。この後に後不動があり、頂上に至るのである。
こうして整理してみて感じるのは、この不動岩というのはいわゆる典型的な巨石遺構ではないものの、金峰山や雲仙普賢岳、阿蘇にまで
関係しているようで、そういう意味でやはり現地探索には行くべきものなのだとつくづく感じた次第である。そしてここは場所的に非常に良い処で
気分が落ち着き、暫くここに滞在していたいという気持ちが強くなる。数億年という岩の重みがなせる技なのかもしれない。
泰山の古代遺跡探訪記topへ